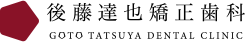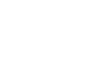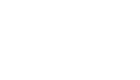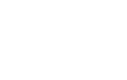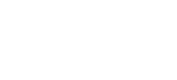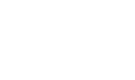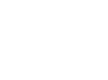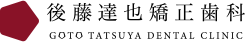歯の矯正では、歯根が長い、顎の骨が通常よりも硬い、などの理由で歯が動きにくい場合があります。
矯正で歯が動きにくいことは、実はそれほど、珍しい現象ではありません。
珍しい現象ではないのですが、中には、まったく歯が動かないケースも(力をかけても、歯が微動だにしない)。
矯正でまったく歯が動かないとき、考えられる主な原因は「骨性癒着(こつせいゆちゃく:アンキローシス)」です。
今回は、「骨性癒着」および「骨性癒着で歯が動かないときの対処方法」について、ご説明します。
目次
■骨性癒着(アンキローシス)とは?
◎歯の根っこと顎の骨がくっついている(癒着している)状態です
骨性癒着(アンキローシス)とは、歯の根っこ(歯根)と顎の骨(歯槽骨)がくっついている(癒着している)状態です。
骨性癒着は歯の根っこと顎の骨がくっついているため、原則として、そのままの状態では、矯正装置で力をかけても歯を動かせません。
■骨性癒着(アンキローシス)が起きる主な原因
以下のような原因によって骨性癒着(アンキローシス)が起き、歯の根っこと顎の骨がくっつく場合があります。
①歯周病・重度のむし歯などによる歯槽骨の炎症
歯周病が原因で歯を支えている顎の骨(歯槽骨)に炎症が起き、歯の根っこと顎の骨がくっついてしまう場合があります。
歯周病のほか、重度のむし歯によって歯の根に起きた細菌感染が骨性癒着の原因になるケースも。
歯の根に細菌感染が起き、歯の根の先端に浸出液の袋(嚢胞:のうほう)ができた場合、嚢胞が原因で歯槽骨に炎症が発生。歯槽骨の炎症により、歯の根っこと顎の骨がくっついてしまうことがあるのです。
②歯の外傷(歯を強くぶつけてしまったなど)
転んだ、事故に遭ったなど、歯を強くぶつけたときの衝撃が原因で骨性癒着が起きることがあります。
歯への衝撃が原因で骨性癒着が起きる主な理由は、歯の根っこを包む歯根膜の損傷によるものです。
衝撃を受けて歯根膜が損傷すると、
- ・靭帯組織(=歯根膜)によって保たれていた、歯の根っこと顎の骨のあいだのスペース
が無くなり(衝撃が原因で、圧縮するような形で歯の根っこと顎の骨の距離が縮まり)、歯の根っこと顎の骨がくっついてしまう場合があります。
③歯が生える途中に生じる原因不明の骨性癒着
歯が生える途中、何らかの原因により、歯の根っこと顎の骨がくっついてしまう場合があります。
歯が生える途中、骨性癒着が起きる原因ははっきりとはわかっていません。遺伝(生まれつき)など、先天的な要素が、歯が生える途中の骨性癒着に関係しているのでは、と考えられています。
なお、先天的な要素が原因と考えられる骨性癒着では、複数本の歯(歯の根っこ)が顎の骨にくっついているケースが多いです。
■骨性癒着(アンキローシス)と癒合歯は違うの? レントゲン検査で骨性癒着を見つけられる?
◎癒合歯は歯と歯がくっついた状態を指します
骨性癒着(アンキローシス)と混同されやすいのが、歯と歯がくっつく癒合歯(ゆごうし)です。
骨性癒着が歯の根っこと顎の骨がくっついている状態であるのに対し、癒合歯は歯と歯がくっついている状態です。骨性癒着と癒合歯は異なります。
◎レントゲン検査、CT検査を受けることで、骨性癒着を発見しすくなります
骨性癒着or癒合歯を発見するには、レントゲン検査やCT検査が基本です。
レントゲン検査のみでも骨性癒着or癒合歯を発見できるときもありますが、より詳しく患部の状態を確認したい場合は、CT検査(撮影箇所を3D(3次元:縦・横・奥行き)で確認可能)の方が望ましいことも。
■骨性癒着(アンキローシス)で歯を動かせない場合、矯正ではどのように対処するの?
骨性癒着が起きている場合、原則として、そのままの状態では、矯正装置で力をかけても歯を動かせません。
矯正治療において、骨性癒着で歯を動かせない場合は、以下のような処置が対処方法として挙げられます。
1.骨性癒着した歯を抜き、インプラントなどの補綴治療で歯を補う
骨性癒着した歯を抜き、インプラントなどの補綴治療で歯を補います。
補綴治療で補った人工歯は動かせません。補綴治療後に行う歯の矯正では、人工歯以外の歯を動かすことで、全体の歯並び・噛み合わせの調和を図ります。
2.歯を脱臼させた後、矯正装置で歯を動かす
ヘーベルなどの器具を用い、骨性癒着している歯を顎の骨から亜脱臼(あだっきゅう)させます。
骨性癒着における亜脱臼とは、以下のようなことです。
- ・歯の根っこと顎の骨をつないでいる靭帯組織の歯根膜を、完全には断ち切らない
- ・歯根膜を完全には断ち切らないよう注意しながら、癒着部分の顎の骨から歯の根っこをはがす
(ご参考までに、通常の抜歯では歯根膜を完全に断ち切る形で歯を抜きます)
歯の根っこを亜脱臼させ、歯根膜の機能(破骨&造骨細胞を分泌する:矯正に不可欠な機能)を残すことで、骨性癒着していた歯を動かして矯正治療を進められる可能性があります。
なお、亜脱臼の処置では注意点も。注意したいのは、亜脱臼後に再度、骨性癒着が起きたり、亜脱臼のダメージで歯が抜け落ちるおそれがある点です。歯を亜脱臼させたからと言って、必ずしも、矯正をスムーズに進められるようになる、とは限りません。
3.外科的な手術を行い、顎の骨から歯の根っこの癒着部分を切り離す
骨製癒着においては、癒着部分が広いor癒着が強い場合、歯を亜脱臼させられないことがあります。
歯を亜脱臼させられない場合は、外科的な手術を行い、顎の骨から歯の根っこの癒着部分を切り離すケースも。
なお、亜脱臼の場合と同様、外科的な手術を行った後、必ずしも、矯正をスムーズに進められるようになる、とは限りません。癒着部分を切り離した後に再度、骨性癒着が起きたり、歯が抜け落ちてしまうこともあります。
【矯正に関するご質問・ご不安がある方はお気軽にご相談ください】
当院は矯正専門歯科のため、骨性癒着に対する亜脱臼などの処置を含め、矯正以外の処置・治療は他院で受けていただく形になります(※)。
(※)必要に応じて、口腔外科機能を持つ歯科or矯正
以外の処置・治療を行う歯科をご紹介いたします。
今回は、「骨性癒着(アンキローシス)が起きる主な原因」および「歯の矯正における骨性癒着への対処方法」について、ご説明をさせていただきました。
矯正に関するご質問・ご不安がある方は、当院までお気軽にご相談ください。相談費は無料です。Zoomによるオンライン矯正相談も承っております。
カウンセリングでは、患者様のお悩み・ご希望をお伺いします。じっくりと、お話をお伺いした上で、日本矯正歯科学会の矯正認定医が一人ひとりの方に適した矯正方法をご提案させていただきます。